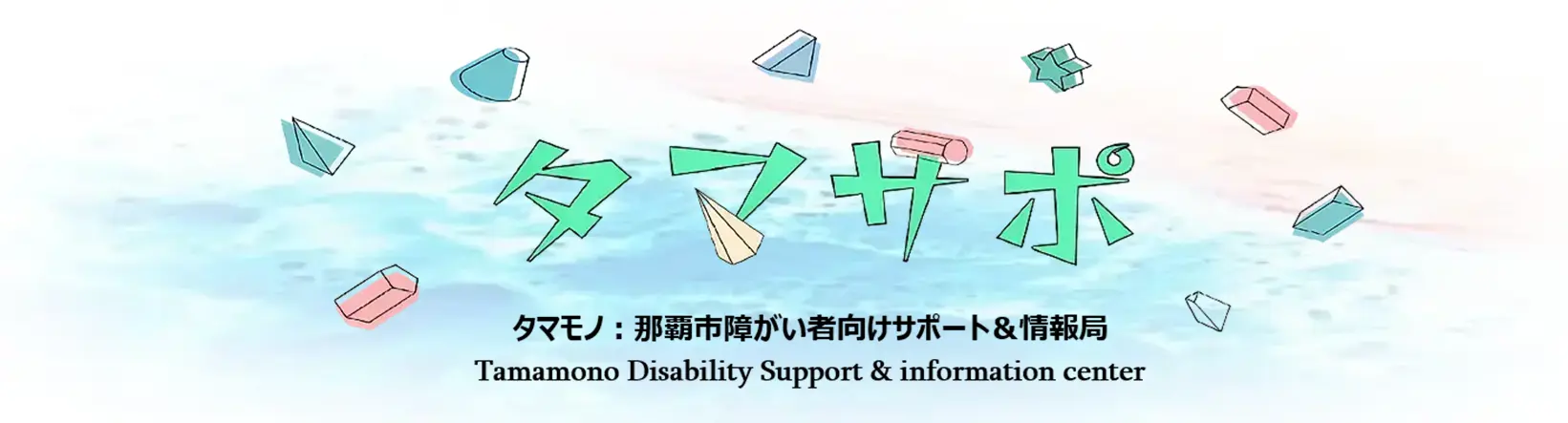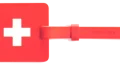内部障害とは、身体の内部、つまり臓器などに障害があり、外見からは分かりにくい障害のことを指します。
内部障害の種類
身体障害者福祉法では、以下の7つの障害が内部障害として定められています。
●心臓機能障害:心臓が十分に血液を送り出せず息切れや動悸などの症状があり、ペースメーカーを入れている人もいます。
●腎臓機能障害: 腎臓の働きが低下し、むくみやすくなったり、貧血を起こしたりします。人工透析治療を受けている人は約35万人(2022年末)、沖縄県では4,935人(2021年末)います。
●呼吸器機能障害:肺や気管支などの呼吸器に障害があり、呼吸が苦しくなります。いつも酸素ボンベを携帯して、呼吸をしている人もいます。
●膀胱・直腸機能障害:膀胱や直腸の機能に障害があり、排尿や排便に困難を伴ないます。ストーマ(人工膀胱、人工肛門)の人も多くいます。また、ストーマのある方のことをオストメイトといいます。
●小腸機能障害:小腸の吸収機能が低下し、消化吸収が不十分になり栄養不足になる状態のことです。原因は手術による小腸切除または小腸疾患です。中心静脈栄養法を受けている人もいます。
●肝臓機能障害:肝臓の働きが低下し、全身倦怠感、食欲低下、吐き気、黄疸、皮膚のかゆみ、からだのむくみ、腹水などの症状が現れます。
●ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫機能障害: 免疫力が低下し、感染症にかかりやすくなります。このウィルスがエイズの原因です。
内部障害は、外見からは分かりにくいため周囲の人からの理解が不足しがちですが、本人にとっては日常生活に大きな困難を伴います。
周囲の人々が内部障害について正しく理解し、適切な支援を行うことが重要です。
また、内部障害であることを周囲の人に示すためにヘルプマークがあります。
🔗ヘルプマーク