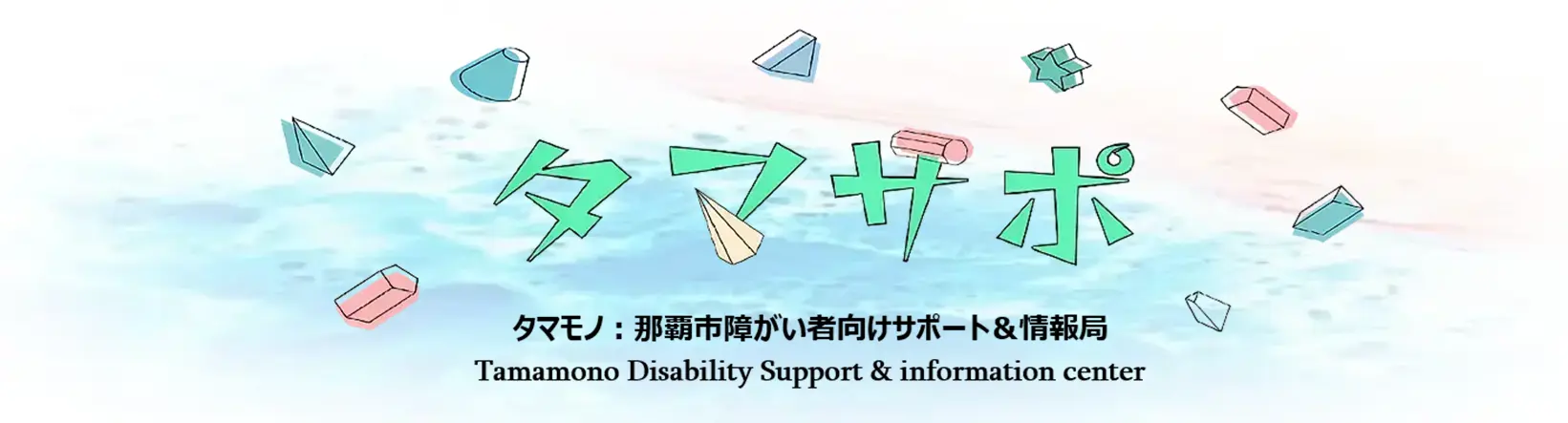障害者制度改革推進会議では、「障害」という表記の見直しに関して、多岐にわたる意見が交わされました。以下、要約です。
「害」の字がマイナスイメージを与えるという理由から、より適切な言葉への変更を求める声がある一方で、既に定着した言葉であり、変更する必要はないという意見も根強く存在します。障害当事者や関係団体の中には、現在の表記に違和感を抱き、🔗障害者権利条約の精神に合致するような表記への変更を望む声も聞かれます。「障がい」や「障碍」など、他の表記への変更や、常用漢字表に「碍」を加えて「障碍」という表記を可能にするといった具体的な提案もなされています。
「障害者」の言い換えについても議論が活発に行われました。「障害のある人」という表現は、「障害」という用語が、障害者があたかも他人を「害」する人であるかのように、 または「害」を持っている人であるかのように捉えられ、不快な思いをされて いる方々がいるという事実があります。一方、「チャレンジド」という表現は、障害を乗り越えるという積極的な意味合いを持つものの、障害者を特別視したり、常に挑戦し続けなければならないというプレッシャーを与える可能性があるという懸念も指摘されています。
これらの議論を通じて、障害者自身がどのような表記を望んでいるのか、当事者の意見を十分に聞き取る必要があるということが改めて認識されました。表記の変更だけでなく、障害者に対する社会全体の意識改革が重要であり、法律や制度だけでなく、日常会話や文書でも適切な言葉づかいを心がけるべきだという意見も多数寄せられました。
結論として、「障害」の表記については、賛成意見と反対意見が対立しており、現時点では結論が出ていません。表記の見直しを行う場合は、障害当事者や関係団体との丁寧な協議と、社会全体の理解を得ることが不可欠です。また、表記の変更だけでなく、障害者に対する社会の制度や環境の改善がより重要であるという意見も多数ありました。
今後の課題としては、障害者に対する社会の意識改革を推進するため、教育や啓発活動の強化が求められます。障害者当事者や関係団体との連携を深め、共生社会の実現に向けて取り組むとともに、障害者に関する法制度や政策の見直しを継続的に行い、障害のある人もない人も共に暮らせる社会を目指していく必要があります。 内閣府:障害の表記に関する意見一覧
●障害者制度改革推進会議は現在廃止されています。